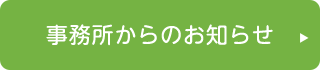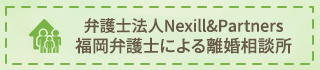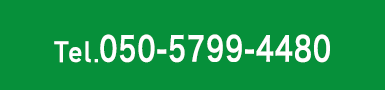労働基準法では、労働者の労働時間を管理することが使用者側に義務付けられています。また、労働時間は労働者の残業代に関わってくることから、なるべく労働時間の集計ミスを減らしたいと思っている方も多いのではないでしょうか。
労働時間の集計ミスをしてしまうと、翌月の労働時間の計算や給与計算も面倒になり、更なるミスが発生しまった結果、従業員に不満を持たれる可能性があります。こういったことを未然に防ぐため、労働基準法上の労働時間の算定方法を見ていきたいと思います。
1. 事業場外・坑内・2事業所以上の場合
一般的に労働者の労働時間は、労働基準法で定められた1日8時間、週40時間労働であり、そのほとんどを事業場内で過ごすことになります。ただ、営業職などは、直行直帰や出張により、事業場以外のところで勤務することも多くあるかと思います。そのような場合、労働時間はどのように算定するのでしょうか?
事業場での勤務以外だと、事業場外勤務・坑内勤務・2事業所以上勤務というのが考えられますので、以下に具体的に説明します。
・坑内勤務…炭坑やトンネルの掘削現場での勤務のことを言います。
・2事業所以上勤務…2カ所以上での勤務のことを言います。
(1) 事業場外勤務
坑内勤務や2事業所勤務といった事例と比較すると一番多い事例で、出社と退社の時間以外は外で仕事を行う方がいる時、労働時間を算定しにくいかと思います。
そういった場合は、労働基準法上の「事業場外のみなし労働時間制」という制度を利用することによって所定労働時間を働いたものとしてみなすことができます。
所定労働時間分(法定の8時間以内)働いたとみなす場合には労使協定の締結は必要なく、就業規則に記載するだけで構いません。
ただし、みなしの労働時間を仮に10時間に設定するとなると、労使協定の締結が必要となり、またこの場合、2時間は法定外時間労働となるため、毎日2時間分の割増賃金の支払いをしなければならなくなりません。
みなし労働時間を決める際には、ご注意下さい。更に、みなし労働時間の場合であっても、深夜労働や法定休日労働に関しては割増賃金が発生するため、注意が必要です。
(2) 坑内勤務
通常の労働であれば休憩時間は労働時間とみなされません。しかし、労働基準法上、坑内労働は坑内に入った時刻から出た時刻まで休憩時間を含めて労働時間とみなします。
例えば、トンネル内での掘削(坑内労働)の場合には、労働者が、坑内へ入坑し出抗するには、安全確認等の時間や、坑口と作業場の距離があるため、移動に時間がかかったりすることが考えられます。
そのため、休憩時間に安全確認の時間や移動時間をかけて外へ出るよりも、そのまま坑内にとどまる方が合理的に作業を進められます。このような事情を勘案して、坑内労働については、休憩時間も労働時間に含めることとされています。
(3) 2事業所以上
例えば、A支店とB支店(AとBは同じ会社)があるとします。その両方(AとB)で働いている労働時間は、労働基準法上通算することになっています。また、A社とB社(別会社)で従業員が兼業する場合も、労働時間は通算する必要があるため、残業代が不払いにならないように注意しなければなりません。
そこで、就業規則に兼業時には事前に申し出るように記載しておくことによって、知らない間に未払い残業代が発生してしまうのを防ぐことが出来ます。なお、兼業している会社の担当者同士で連絡を取り合い情報共有することが大切ですが、一般的には後で働くことになった事業所にて残業代を支払うのが適切ですので、そのあたりも踏まえて連絡してみましょう。
もし、兼業を認めない場合は兼業の禁止を就業規則や雇用契約書に事前に明記しておき、面接時に本人に了承を得て採用することがトラブルを防止する一つの方法です。
2. 専門業務型裁量労働制
この制度は、研究・開発職や企画職といった、労働の質や成果によって報酬が決定される専門的業務(厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務19種 ※1が対象)において、実際の労働時間によらず、一定の労働時間だけ働いたとみなされる制度です。そのため、業務の性質上その実施方法(業務遂行の手段や方法、時間配分等)を労働者の裁量に委ねる必要があります。
この制度を使用する場合は、労使間で書面による協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。会社に過半数を超える労働組合がない場合は、過半数代表者と協定を結ぶようにしましょう。
また、当該制度を導入した場合であっても、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合、深夜労働や法定休日労働の場合は、割増賃金が発生することは、「事業場外のみなし労働時間制」と同様ですので、ご注意ください。
3.まとめ
今回は、労働時間の算定方法についてまとめました。外回りが多い職種(営業)や特殊(研究・開発職や企画職)な職種を持つ会社では特に注意が必要です。
もし、人員を増やす場合や新規募集する職種の場合、今回説明した内容を踏まえて雇用契約書や就業規則の見直し、面接時の確認事項など、労務面での再考が必要ですので、そこも注意してみてください。
※1 業務内容は省略しています。
(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システムの分析又は設計の業務
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材もしくは編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) コピーライターの業務
(7) システムコンサルタントの業務
(8) インテリアコーディネーターの業務
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 証券アナリストの業務
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12) 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務